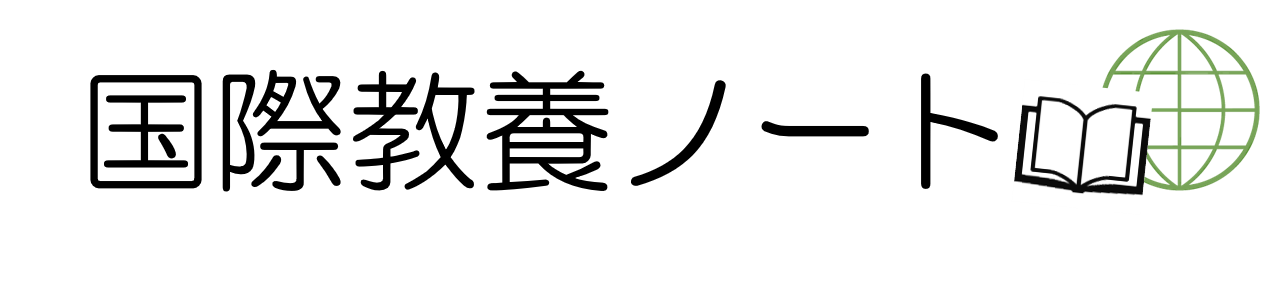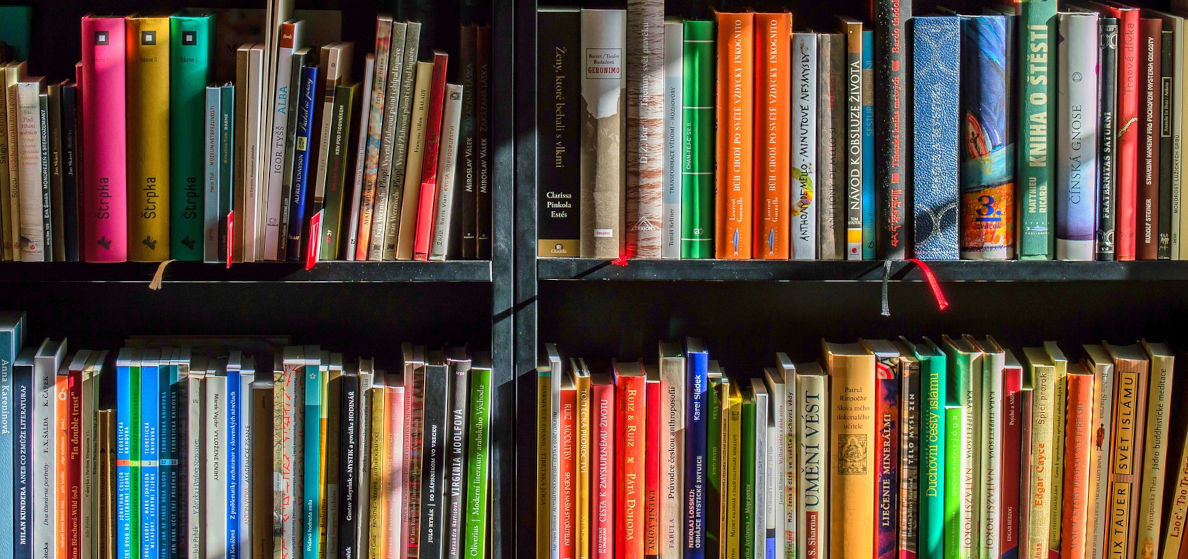翻訳書の和文タイトルは、原書と大きく異なっていることがあります。同じ本だと気づきにくいケースもあります。
本記事では、著名な翻訳書で、タイトルが日本語・英語で大きく違うものを紹介します。
主にビジネス書系の本を対象とします。
翻訳書のタイトルの意味が英語版と異なる本の例
『イノベーション・オブ・ライフ』(クレイトン・M・クリステンセン, ジェームズ・アルワース, カレン・ディロン)
『How Will You Measure Your Life?』(Clayton Christensen, James Allworth, Karen Dillon)
直訳すると「あなたは自分の人生をどう評価するか?」です。イノベーションは関係ありません。おそらく、著者の代表作に『イノベーションのジレンマ』という名著があるため、販売戦略上「イノベーション」という単語を使ったのかと推測します。
『21世紀の貨幣論』(フェリックス マーティン)
『Money: The Unauthorized Biography』(Felix Martin)
直訳すると「貨幣:非公認の伝記(略歴)」のような意味です。過去に焦点を当てたタイトルだったのを、読者ウケを意識して「21世紀」という未来志向のタイトルにしたのでしょうか。
『ティール組織 ― マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』(フレデリック・ラルー)
『Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness』(Frederic Laloux)
直訳すると「組織の再発明:人間の意識の次の段階にインスパイアされた組織を創造するためのガイド」です。日本語の副題がやや近そうですが「マネジメントの常識を覆す」という言葉は原書にありませんし。「ティール組織」という用語は本書のメインのテーマですが、敢えてそれをタイトルにしたほうがインパクトが大きいと判断したのでしょう。
『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』(リンダ グラットン (著), アンドリュー スコット)
『The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity』(Lynda Gratton, Andrew J. Scott)
直訳すると「100年人生:長寿時代に生きて働くこと」です。「LIFE SHIFT」という単語は出版社の造語なのでしょうか。日本人読者へのインパクトを意識したのでしょう。
『フランス人は10着しか服を持たない』(ジェニファー・L・スコット)
『LESSONS FROM MADAME CHIC』(Jennifer L. Scott)
直訳すると「マダム・シックからのレッスン」です。日本語タイトルは全く意味が違います。日本の読者の中でも、特定の層をターゲットに売ろうという意図が見えます。
『失敗の科学』(マシュー・サイド)
『Black Box Thinking: The Surprising Truth About Success』(Matthew Syed)
直訳すると「ブラックボックス思考:成功についての驚くべき真実」となります。日本語版のように「科学」と言ってませんし、内容的にも科学的な論考の本ではありません。
まとめ
以上のように、販売戦略からインパクトの強さや分かりやすさを重視して、原書と全く意味の違う日本語タイトルを付ける例があります。翻訳書を読む際は、ぜひ原書のオリジナルの英語タイトルにも注意したいものです。