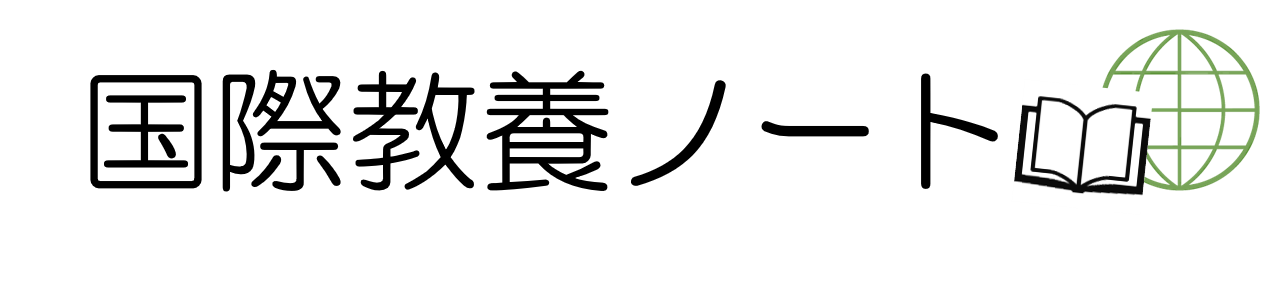社内での人事評価を高めるため、下げないために、重要なポイントはいくつかあります。その中で、盲点になりやすいポイントをお話します。私自身が、この部分を怠ったため、ひどい目に合ったことが何度かあります。自省もこめて書きます。
社内の人事評価の重要ポイント
<人事評価制度の前提>
ここでは、ある程度の規模の企業、および企業内での部署を想定します。少なくとも2階層以上で評価がされる前提とします。
つまり、
- 一次評価者 = あなたの直属の上司(たとえば課長)
- 二次評価者 = あなたの直属の上司の上司(たとえば部長)(★実質的な最終評価者)
とします。それ以上の階層で、例えば、本部長などが最終評価をすることもあるかもしれませんが、実質的には影響が少ないです。
ここで、以下の前提がある場合が多いです。
- 一次評価者(課長)は、基本的にあなたの味方です。あなたの評価が下がると、自分の評価も下がります。どうにかしてあなたを引き上げようとするでしょう。(あなたがそこそこ有能であることが前提ですが)
- 二次評価者(部長)は、最終決定権があります。ただし、評価を決める際は、一人で決めることはなく、評価者会議のような場で実質的に決まる場合が多いです。これは、例えば、部長とその配下の課長(複数名)で構成されるのが通常です。
ここで、最終的にあなたの評価を左右するのは、「あなたの斜め上の上司(つまり隣の課の課長)」となるケースが多くなります。
<斜め上の上司が決定権を持つ例>
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
部長
├── 課長A ── あなた
├── 課長B ── あなたのライバル
├── 課長C (★実質的な決定者)
このように部長の下に3人の課長がいて、あなたの上司は課長A、あなたのライバルの上司は課長Bとします。
評価者会議のメンバーは、部長、課長A, B, Cです。ここで、部長は、最終決定権はあるものの、あなたの普段の仕事ぶりを直接よく見えない場合が多いです。
あなたの上司の課長Aは、あなたを推すでしょう。一方、ライバルの上司の課長Bは、ライバルを推すでしょう。
この場合、キャスティングボートを握るのは、課長Cになります。普段、あなたが課長Cに仕事ぶりをアピールしていれば、課長Cはあなたを推してくれるでしょう。最終評価者の部長は、課長Cの意見を重視して、決定をするはずです。
つまり、「斜め上の上司」へのアピールが重要になります。
私自身、勤務先の会社で何度か、この観点を見落としていて、自分の真上の課長・部長にのみアピールする形をとっていたため、斜め上の上司に仕事が認知されず、不当に低い評価を受けたことがあります。
斜め上の上司へのアピールの方法
では、「斜め上の上司」、つまり隣の課の課長へのアピールして、自分の評判を上げるにはどうすれば良いでしょうか。
今思えば、こうしておけば良かったと思うことがあります。
<斜め上の上司へのアピール方法の例>
- 「斜め上の上司」の課の社員との面識を作り、拡大させる。それをツテに、その課に頻繁に足を運び、顔を名前、自分の仕事などを覚えてもらうようにする。
- 自分の仕事と、「斜め上の上司」の課の仕事の接点・共通点を調べる。そこから、議論を持ちかけるなどする。
- 部内の複数の課にまたがる横断的な仕事に積極的に応募して、名前を売る。
こうしたことを日頃から意識して行動し、評価を積み上げることが重要になると考えます。
まとめ
社内・部内の人事評価の仕組みをよく把握しておくことです。表面上の制度ではなく、実質的な議論のされ方を知っておくことです。そして多くの場合、「斜め上の上司」への覚えが良いかどうかが、実質的な評価を分けるポイントになりがちです。アピールの仕方を工夫しましょう。