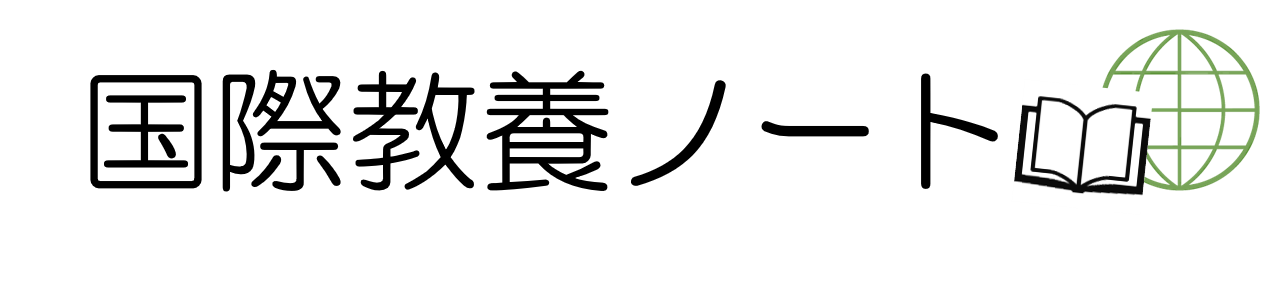将来のキャリアプランに不安がある場合、打開策として、組織の中の「グローバル人材」になるという手があります。キャリアパスや待遇の面で新たな可能性が開けてきます。
今回は、グローバル人材になるメリットと具体的なプロセスについて、私の経験も交えて書きます。
グローバル人材になるメリット
一般的な企業では、英語力があり外国企業との交渉など国際業務を任せられる人材を、「グローバル人材」として、一般の人材と区別して扱われます。
明確な人事上の区分は無い場合でも、暗黙のうちに特別視されるでしょう。
「グローバル人材」になれば、国際業務や海外赴任など、社内で担当できる業務の選択肢が広がります。特に長期的なキャリアパスの幅も広がるため、精神的に余裕が持てるようになります。
転職に有利になることも、言うまでもありません。
逆に、国内業務しかできないドメスティック人材であり続けると、企業の業態変化によっては社内で居場所がなくなります。
リスク回避のためにも、「グローバル人材」を目指すことを選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
グローバル人材になる方法と必要スキル
私の経験に基づいて整理すると、社内で「グローバル人材」の地位を確立するには、次のステップが有効と考えます。
- 英語を事前に徹底的に勉強しておく。英検やTOEICのスコアで、グローバル人材になれる能力と覚悟をアピールする。
- 国際業務を希望することを、社内の人事面談などでアピールしておく。
- とにかく早めに、国際業務を担当するチャンスをつかむ。そのために社内でアンテナを張っておく。
- 国際業務で、結果を出す。同時に、次の国際業務につながる布石をうつ。
- 次回の国際業務で、さらに実績を上積みする。その繰り返しで信頼を得る。
- 海外勤務を経験し、グローバル人材として地位を固める。
私自身の経験を少し書きます。
新卒で入社後、6年ころまで、海外の業務の経験はありませんでした。ただ海外旅行は好きだったため、多少の興味があった程度です。
ある時、職場で英国企業との共同プロジェクトの話が持ち上がりました。当時、私が部署内でTOEICのスコアが最も高かったため、担当者に抜擢されました。そこで5回ほどの出張と現地での業務を通じて実績を残しました。
そこから、海外事業の面白さを知って、グローバル系の業務をキャリアの軸にすることを決めました。海外勤務への道も開けました。
帰国後も、国際事業の担当をしたり、研究開発でも外国企業との協業を担当するなど、国際業務が軸になっています。
グローバル人材の育成方法
企業の人事や人材開発の担当の方は、グローバル人材の育成に悩むこともあるでしょう。
上記にあげたようなプロセスを社員が実行しやすい環境があれば、社員の行動も促せるのではないでしょうか。
社内でTOEICや英検などの受験を推奨し、社員のスコアや取得資格を把握すること、国際業務を希望する社員を柔軟に異動させ経験を積ませること、ポストを公募することなどが考えられます。
また、国際業務で実績をあげた社員を高く評価・処遇することも大事です。冷遇すれば、他社に転職してしまいます。
まとめ
組織内で「グローバル人材」の地位を確立すれば、キャリアパスの選択肢が増え、精神的にも余裕が持てます。まず、多少無理してでも実績を作るよう努めましょう。最低限の英語力をつけておくことが第一歩です。